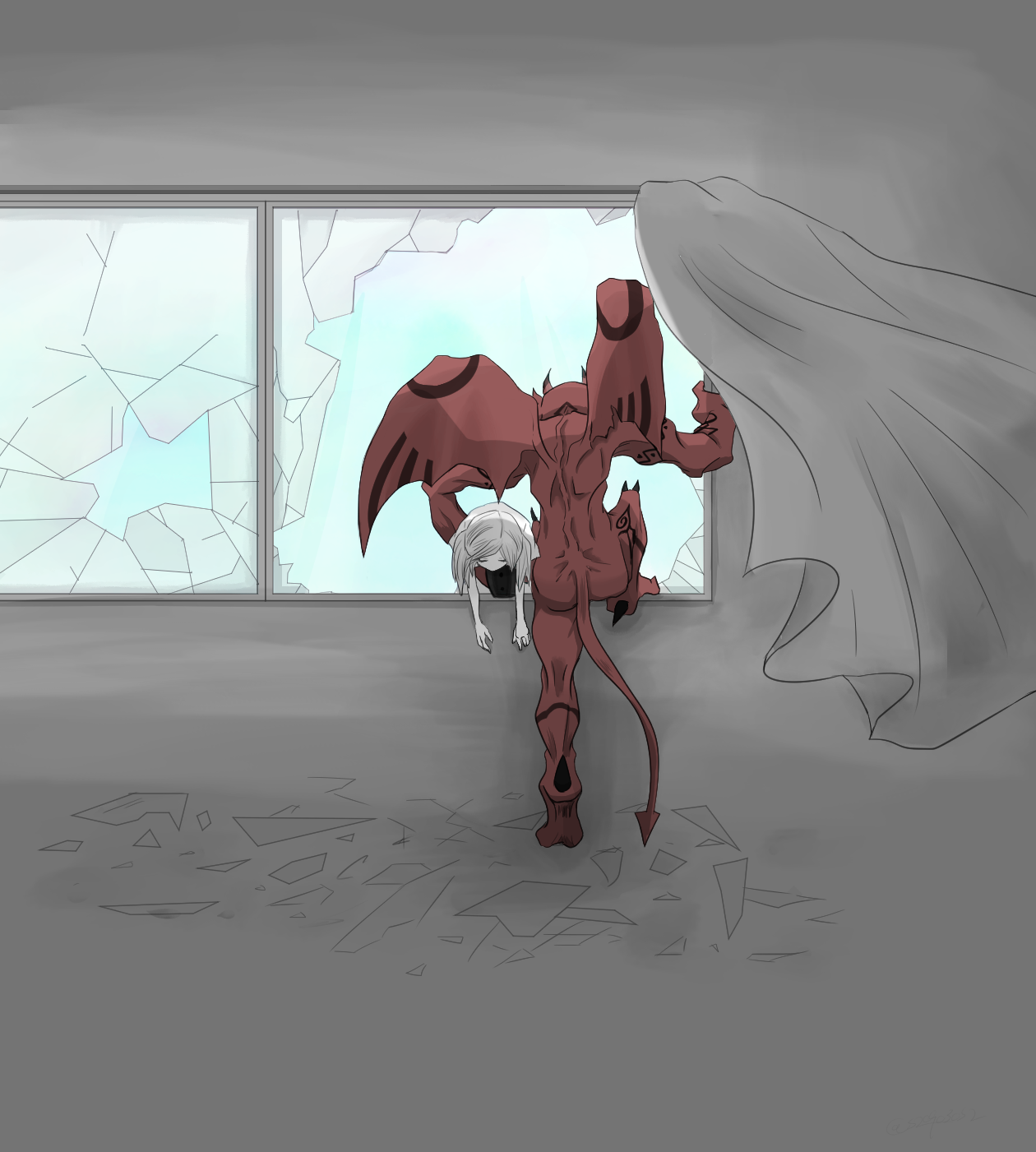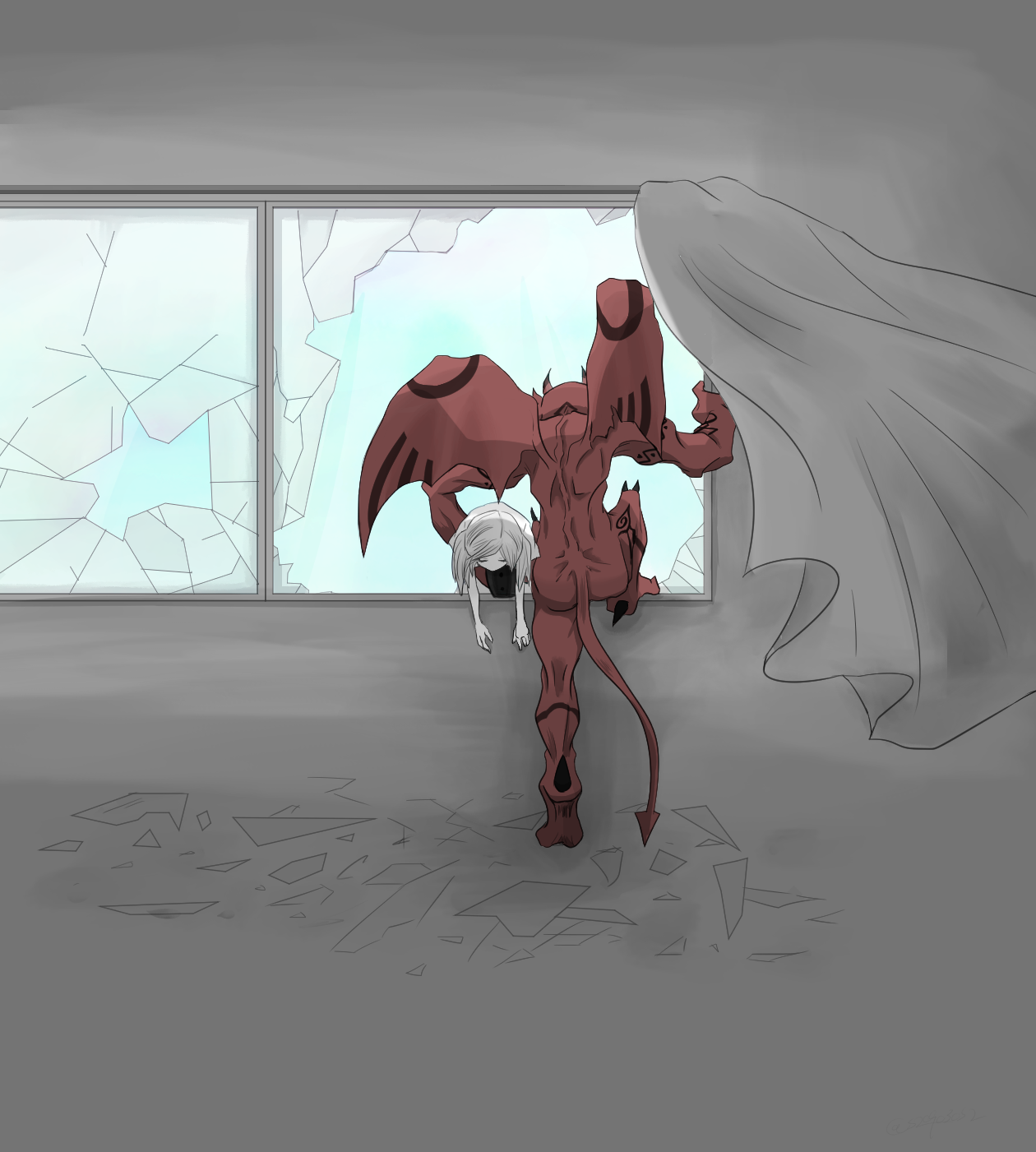◆ ◆ ◆
「ごめんね手鞠ちゃん。当番じゃないのに手伝ってもらっちゃって」
放課後。手鞠と柚子は二人、図書館で本の整理をしていた。
本当は六年生が三人で行う予定の作業だったが、急遽二人が休んでしまい──ピンチヒッターとして手鞠に頼んだのだ。
「いいんです。柚子さん一人じゃ大変ですもん」
「ありがとう。でも、門限とか大丈夫なの?」
「はい。母には説明してありますし……後で連絡して、迎えに来てもらうことになってますから」
ようやく作業が終わった頃には、既に一部の教師達も帰り始めていた。
きっとここにはもう数人しか残っていない。学校は、とても静かだ。
「じゃあ、終わったこと先生に言ってくるから。先に支度しちゃってて。お母さんに電話もね」
そうします、と返事をする手鞠を置いて、柚子は図書室を後にする。
手鞠は言われた通り母親に電話をしようとし────何故か圏外になっていたので、不思議そうに首を傾げた。
「時間、少し置いたら繋がるかなあ」
図書室も、廊下も、既にカーテンは閉められている。
だから二人とも──空を覆うオーロラの光に、気付かない。
「……あ、そうだ」
柚子は図書室棟の一階まで降りると、職員室には行かず寄り道をした。トイレを済ませておきたくなり、教員用の化粧室を拝借する。
扉の前に立つと、何やら中が明るい事に気付いた。電気が付いている? それにしては少々薄暗い。僅かに恐怖心を抱きながら、柚子はそっと扉を開けた。
個室は全て空いていた。中には誰もおらず、電気も着いていなかった。
だが────窓の外が、光っている。
「……!!」
柚子は咄嗟に曇りガラスを開けて──驚いた。オーロラだ! 早速ケータイを開いた。写真を撮って、ネットに書き込もうと急ぐ。だが
「え、圏外!? なんでこんな所で……」
接続を繰り返す。しかし何度やっても繋がらない。
カチカチとキーを押す音に混ざって────誰かの叫び声が聞こえてきたのは、そのすぐ後のことだった。
びくりと体が跳ねる。聞こえたのは校庭の方からだ。
まるで、お化け屋敷の中で聞くような絶叫。……柚子は思わず個室に逃げ込んだ。扉を閉め、必死に息を潜めようとする。
今度は大人の声が聞こえた。教員達も騒ぎ始めているのか。……声が遠くなる。多分、悲鳴がした校庭に行ったのだろう。
そして次に、ガラスが割れる音を聞く。
近い場所だと咄嗟に思った。でも──どこの窓? ああ、そうだ、この上だ。図書館のガラスが割れたんだ。
「……! 手鞠ちゃんが……!」
嫌な予感がして、咄嗟にトイレを飛び出した。階段を駆け上る。廊下を走る。
そして、図書室の前。
すぐに扉を開けて、彼女の無事を確かめる──
「あっ」
────事が、出来なかった。
扉は僅かに開いていた。
その隙間から見えた中の様子は、柚子を凍りつかせるには十分な光景だった。
先生、どこにいますか。早くここに来てください。助けて下さい。
助けを呼びたくても声が出ない。決して声を出してはいけないと、体が先に理解していたから。
凍りついた筈の体はいつの間にか扉から離れ、図書室から気付かれないであろう位置へ移動していた。両手で口を押えながら、呼吸の音さえ漏れないように。
「────」
そこには、化け物がいた。
化け物が、子供を攫っている。
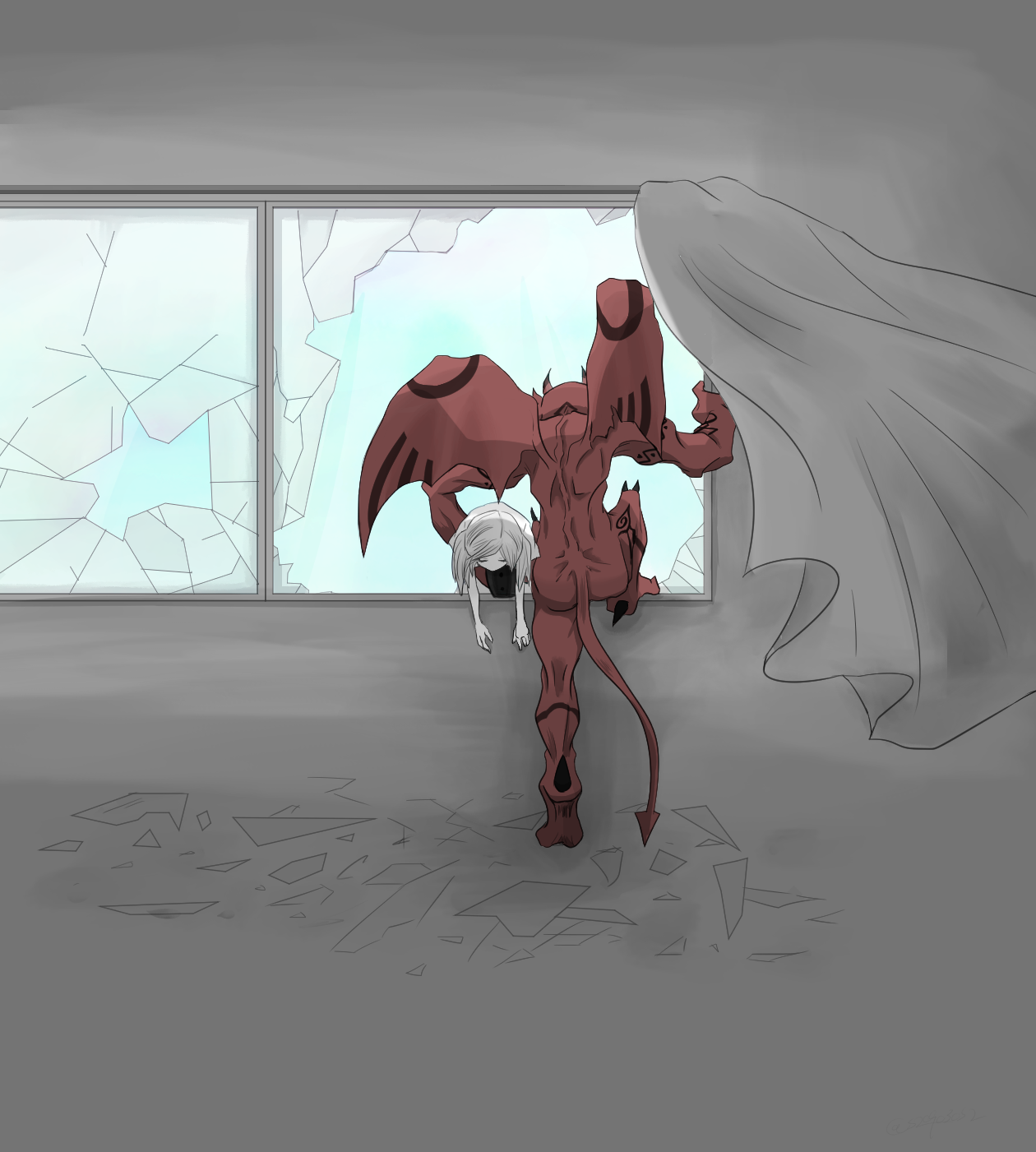
◆ ◆ ◆
「なに、あれ」
呆然と花那が呟いた。
ああ、ママの言う通りだ。本当にテレビや本で見るような、オーロラらしいオーロラだった。
見覚えのある薄緑色一色の、空に浮かぶ光のカーテン。
「……リアライズゲート……」
「いくらなんでも……大きいとかじゃないよ……ねえ……! 何あれ……!?」
「い、言わなきゃ……! 二人に電話は……!」
「出来ないよ! 圏外になってる……! なんで!? さっきまでママと電話出来てたよ!? なんで圏外なの、こんな場所で……!!」
「……まさか……アレのせいなのか?」
家の外がざわつき出す。近所の人々が、次々と外に出て空を見上げる。
それに続くように、蒼太も靴を履いて外に出ようとした。
「!? 蒼太、どこ行くの!?」
「家に……自転車取ってくる……」
「何で……」
「だって! 連絡取れないなら行くしかないだろ!」
「で……でも、外出たら危ないよ! あそこから出てくるのが、二人やテリアモンみたいな子かわからないんだよ!? もし昨日みたいなデジモンが──」
出てきたら、どうするの。
そう言おうとして気付く。
仮にそれが、自分達の近くに現れたとして。家の中に逃げ隠れたとして。
それこそ、本当にどうしようもない状況に成り果てるのだと。
「…………っ」
ここに彼らはいない。
自分達でどうにかできる問題ではない。
相手が危険なデジモンだったとしたら、隠れたところで──
「────後ろ乗って」
「……え」
「私の後ろ乗って! 自転車! 蒼太の家まで送る……! 走ってたら時間かかるよ!」
◆ ◆ ◆
不思議な光の噂。
見ると幸せになれるらしい。
噂は本当だったと、少年は喜んでいた。
「おおおおお! オーロラだー! すげー!」
空に浮かぶ光のカーテンはまさにオーロラそのもの。誠司はそれに、昨日見た光と似た何かを感じていた。
それに、昨日の今日だ。興奮しないわけがない。
都合が良いことに周囲に人はいない。背負っていた大きめのリュックを、しっかりと腕に抱える。
「ユキアグモン! 見てみろよ! すっげーぞ!」
呼ばれて、ユキアグモンが中からひょっこりと顔を出した。
──空を、睨むようにじっと見上げる。そうとも知らず、誠司ははしゃいでいた。ケータイで写真を何枚も撮ったりしながら。
「なあ、今度はでっかい恐竜出てくるかな! ティラノサウルスみたいなさ!!」
「……きゅー」
ユキアグモンが鳴き声をあげたことでようやく、誠司はユキアグモンの様子に気付く。……警戒するというより、怯えているようだった。
「ど、どうしたの。ユキアグモン。……怖いの?」
「せーじ、せーじ」
「……とりあえず、もっかい入っとくか? そうすれば見なくて済むし……」
「とーく。ぜーじ、とーぐ」
「? トーク? 話すの?」
違うと言いたげにユキアグモンは首を振る。
「とーく、はじ、る」
「はじる? ……ああ、遠くに走るのか! わかった! どっかの店とか入ろうな。アレが怖いんだろ?」
「ぐるるるる……」
「よーし、じゃあ全力疾走だ!」
「ぎー! いぞぐ! いぞぐ!」
背負い直したリュックから聞こえる声は、やはり怯えているようだった。走りながら励ます。
「後でビッグニュースになるぜアレ! こんな場所にオーロラなんてありえねえもん!」
「いそぐー! ぐー!」
「わかったわかった。そんなに怖いの? お前が出てきた光だってきっと似た奴だぜ? 今噂になってんだけどさ、あの光はハッピーになれる光なんだ!」
そう言って、もう一度空を見上げた。
「だから、怖がらなくたっていい……」
上空を、大きな影が走る。
「……お?」
鳥にしてはあまりに大きな影。
「何だ、今の……」
「グルルルルル……!!!」
リュックの中でユキアグモンが唸っている。どうしてかは分からない。
過ぎ去った影が戻ってきた。
ふっと視界が暗くなった。
何かの影の中に自分はいた。
背中の唸り声が大きくなる中、誠司は視線を逸らせない。
そこには
「────俺が、見えるな」
オーロラの逆光でよく見えない。
だが、その姿はあまりにも恐竜などとはかけ離れていて
「じゃあ、お前もだな」
“幸せの光”から出てきたとは信じられない、おぞましいものだった。
それは、漫画やゲームに出てくるような化け物の姿。
角が生えた、赤い肌の悪魔。
「────ぁ、れ……?」
リュックサックが動く。ユキアグモンが飛び出そうとしている。──だが、出られない。もがいているうちに、肩紐が誠司の肩から落ちて行った。
アスファルトの上、リュックサックが唸りながらもがく。悪魔は気にしていないようだった。歪んだ顔で微笑みながら、誠司に手を伸ばしていた。
何が起こっているのか、理解が出来る訳もない。悪魔の腕には、覚えのある形をした黒いリングがはめられている。
そして────もう一方の腕には、「先客」が抱えられていた。
「早くしねえと……死んじまいそうだ……でも、ははは……これで、デジタルワールドに帰れる……」
デジタルワールド。
どこかで、聞いたような言葉だった。
「……──そーちゃん」
頭を掴まれた。
視界が黒くなる。
意識が白くなる。
そして
「…………ぎー。ぎー」
ユキアグモンがようやくリュックから這い出た頃。辺りにはもう、誰も残っていなかった。
◆ ◆ ◆
走る。走る。走る。
少し傾斜のある閑静な住宅地。外に出て物珍しげに空を見上げる人々を避けながら、蒼太と花那は必死にペダルを漕いでいる。
人々は、二人の事など気にも止めない。「オーロラを近くで見たいのだろう」程度にしか、きっと思っていないのだ。
ただの異常気象ならば。あそこから何も出てこないのならば。出てきても怖くない何かだとわかるならば、こんなに必死になる事もないのに。
何が現れるかわからない──という事以上に、言い様のない恐怖が子供達の背中を押していた。
走る。走る。走る。
もう随分と走ったような気がする。実際は数分しか経ってないのだろうが。
普段より長く感じる道。
生温い風。
空にあれだけの光があるのに、薄暗い道。
何故だか人が少なくなっていく大通り。
「……な、なあ、あのオーロラ……」
「何!? 今、話してらんない!」
蒼太の前を走る、花那は真っ直ぐ前を向いたまま答えた。
「ご、ごめん! でも……いつから出てたんだろうって、思って」
「わ、わかんないよ! ……でも、十五分は、経つ、かも……!」
「じゃあさ! もう、何か出てきても……おかしくないよな!?」
「そ、そうだけど! わかんないって! ……ねえ、あそこまでこんなに遠かったっけ……!?」
「──!! 花那! 今の……!」
「何!?」
「人が倒れてた……!」
蒼太が慌てて自転車を止めた。少し遅れて、花那もブレーキをかける。
「……ほら、あそこに!」
蒼太が指差した先には、確かに女性が倒れていた。
「や、やばいよ……! 電話だって繋がらないのに……!」
「…………なんで、ランドセルが落ちてるの?」
「ランドセル? そんなの今どうでも……!」
「だって変だよ!」
倒れているのは大人の女性だった。なのに、彼女の傍にはランドセルが落ちていた。
花那が駆け寄る。女性は気を失っているが、怪我をしている様子はない。……それどころか
「……蒼太、そのランドセル……なんか、綺麗じゃない?」
車や自転車に轢かれたにしては、砂も傷もついていない。
「そもそも私たち、車とすれ違ってないし、これ、事故とかじゃない……」
「病気だったらそれこそヤバいよ! 救急車を──」<
「────何でまだ、子供がいるんだぁ?」
野太い声が聞こえた。
二人の背中に、耳に、響くように。
「「────」」
空を見上げる。赤い肌をした誰か、浮いていた。
「ここは……ゲホッ、あいつが、回った、筈だろうがよぉ」
それが何の生き物なのか、二人にはすぐ分かった筈なのに。
喜びはない。胸の高鳴りもない。そういった感情は何一つ湧かなかった。
何故ならその目つきが、手に携えた三つ又の槍が、その雰囲気の何もかも──子供でも分かる程、敵意に満ちていたからだ。
なんで。どうして。
そんな言葉ばかりが頭に浮かぶ。一刻も早く逃げなくては。分かっているのに、足に力が入らない。
赤い悪魔のようなデジモンは、ゆっくりと地面に降り立った。息を切らせながら、しかしどこか嬉しそうな顔で近寄ってきた。
「……来るなよ……」
上擦った蒼太の声に耳を傾けることなどせず、ゆっくりと
「来るな……!」
────ピーポー、ピーポー、ピーポー。
悪魔がふと視線を逸らした。初めて聞く音に首を傾げる。
サイレンの音。パトカーか救急車か分からないが、どこか遠く聞こえてきた。
──そのありふれた日常の音に、二人の恐怖が一瞬だけ紛れる。
「……!」
花那が咄嗟に携帯電話を取り出した。電波のマークが、一本だけ立っていた。
そして今度は、電話から音が鳴り響く。
「……──この番号……」
「さっきからうるせええぇ……頭痛えんだよぉ……こっちはぁぁあ!」
顔を醜く歪ませながら、視線を子供達へと戻す。
「! 花那! 早く出て!!」
「もしもし! もしもしコロナモン! お願い助けて!!!」
『────聞こえたな!? 声の位置は!』
『こっちだ!!』
「……おい、お前今……コロナ“モン”って、言ったか……?」
「助けて!! 助けて!!」
「俺たちここにいるよ!!」
「おいいぃぃぃ……答えろ糞ガキぃ!!」
『ニオイが強い! すぐそこだ!』
『────ガルルモン! いた!! 「そこにいる!!」
子供達の真上を、大きな影が走る。
「コロナフレイム!!」
「フォックスファイアー!!」
悪魔が、紅い炎と青い炎に飲み込まれた。
◆ ◆ ◆
「ぎゃ、あ、あぁああっ……!」
赤い悪魔が炎の中で喘ぐ。即座に槍で炎を払い退けると、翼を広げて空を舞った。
「────っなんでだああああっ!! なんでこんな所にデジモンがいやがる!?」
「それはこっちのセリフだ! 『ブギーモン』!!」
ガルルモンが吠えた。コロナモンはガルルモンの背中から飛び降りると、子供達のもとへと走る。
「二人ともケガは!? ……大丈夫だね!?」
「こ、コロナモン! コロナモン! 来てくれた……!」
花那がコロナモンを抱き締める。彼女の背中を撫でる腕は、既に酷く傷ついていた。
「コロナモンお前……! 怪我してるじゃんか! ガルルモンも……!」
「大丈夫だ。とにかく二人はここから離れないで! ──ガルルモン!」
コロナモンが子供達から離れる。ガルルモン前足で地面を蹴り、大きく吠えた。──子供達を守るように、周囲に氷の壁が現れた。
「アイスウォール!! ……コロナモン、援護を!」
「背中に乗せて! コロナフレイムは多用できない!」
「てめーも質問に答えねえのかあぁ!! なんで俺を知っている!? 何故デジモンがここにいる!?」
ブギーモンと呼ばれたデジモンが槍を振るう。ガルルモンはそれを飛び越え、後ろ足でブギーモンを蹴り飛ばした。
「がッ……!」
「ここに来る前、僕らはお前たちの仲間に会った! 別個体のブギーモンにだ! そいつは自分から名乗っていたよ!」
「お前だけじゃない……俺たちも聞きたい事が山程あるんだ!」
コロナモンはガルルモンの背から飛び跳ね、炎を纏った拳でブギーモンを殴りつける。ブギーモンは勢いよく地面に叩き付けられた。
「……成熟期なのに俺にやられるなんて……やっぱりお前も、リアライズした時のダメージは受けてるんだね。最初はびっくりしたよ。何でリアライズしてすぐに飛べるんだって」
「はー、は────ぁ、ハッ……」
「……じゃあ、先に会ったデジモンは……どうしたの……?」
花那が呟く。ぴくりと、ガルルモンが耳を動かした。
「……花那、それは」
「余所見すんなああぁぁっ!!」
「! このっ……」
ブギーモンがガルルモンへ槍を投擲する。咄嗟にコロナモンが悪魔の膝を蹴り払った。ガルルモンの皮膚に槍先が掠り、赤い血飛沫が跳ねる。
「が、ガルルモン! ごめんなさい……!」
「大丈夫! 君のせいじゃない!」
「今度こそだ、ガルルモン! ──あの子たちには、もう見せたくない……!」
「俺をやれると思ってんのかぁ!? てめぇら空も飛べないくせに!」
「飛べないさ! 俺たちは! でも、今のお前は空を飛ぶしか出来ないだろ!!」
「……!」
ブギーモンの額に血管が浮き出る。──挑発に乗ってくれた。それなら奴はきっと、飛んで逃げていく事はしない。
「調子に乗りやがって……! てめぇらどうせこっちに逃げて来た死にぞこないだろうがあッ!! 大人しく死んでろよおぉ!!」
槍を拾い上げたブギーモンは、コロナモンめがけて急降下する。ガルルモンが炎を吐きブギーモンを包み込んだ。──だが、それは殺す為のものではない。
「──コロナモン!」
ガルルモンはコロナモンを背に乗せ、飛び上がる。ブギーモンと同じ高度になった瞬間、コロナモンが背中から飛び跳ねた。
コロナモンは全身に炎を纏う。肉体そのものが、一つの大きな火炎弾と成る。
「プチプロミネンス!!」
槍先がコロナモンへと向けられるより先に──コロナモンがブギーモンの顔面へ激突した。
「────ごっ、ぁぁ」
「……っの! まだだ!!」
跳ね返る。コロナモンはブギーモンの角を掴み、体を大きく回転させ──背中を殴りつけた。
再び落下するブギーモン。しかし叩き付けられる寸前に翼を広げた。
「今だ! ガルルモン!!」
コロナモンの言葉に警戒したのか、ブギーモンは体勢を整え直そうと浮上を試みる。
ブギーモンの翼が、ちょうどガルルモンの背丈よりも高くなった。瞬間────
飛び上がったガルルモンが、ブギーモンの片翼を骨ごと食い破った。
「────ぎゃああああああああああああああッッ!!!!!」
ガルルモンはそのまま腕に噛み付き、地面へ叩き付け、全体重をかけ圧し掛かる。
コロナモンは三又の槍を奪い取ると、それをブギーモンの首に突きつけた。
「俺たちはお前を殺さない!」
そう、叫びながら。
「でもお前の負けだ! 俺たちの勝ちだ!」
「……の野郎おおおおおっ! 何言ってやがる!!」
「お前はもう飛べない。戦う力だって無いはずだ。僕らには絶対に勝てない」
「それはてめえらもだろうが! この世界で! ろくに力が出せるワケがねえ! なのに何でだ!? どうして俺は!?」
……その問いに、二人は答えなかった。
悪魔の言葉は正しい。先程の作戦だって賭けだった。事前に別個体のブギーモンと戦っていなければ──相手がどれほど弱っているのか知らなければ、叶わない作戦だった。
デジタルワールドにいる頃より技の威力が劣っている事は、彼ら自身わかっている。自分達が「ろくに力の出せない死にぞこない」である事も間違いない。
同時に──目の前のブギーモンには、辛うじて飛べる程度の力しか残ってない事も。
無理もないだろう。そもそもリアライズした直後に、これほど動けている方が信じられない。
「……そ、そいつ……どうするの?」
氷壁の内側から、不安そうな蒼太の声が響く。
コロナモンとガルルモンは申し訳なさそうに目線を向けると、再びブギーモンを睨みつけた。
「──僕たちはお前を生け捕りにする。聞きたい事があるんだ。だから、殺さない」
「ハッ……話すと思うかぁ?」
「話せば生きたまま解放するって約束する。でも……誰かを襲うようなら、この子たちにまた手を出すようなら、その時は、あのブギーモンみたいに」
「殺すってか!? はははぁっ!」
「笑うな。……本気だよ。俺たちだって命をかけてここまで来たんだ。お前だって死にたくはない筈だよ。よく、考えて」
目の前で行われる命のやり取り。
子供達は、息を呑んだ。
「……花那、蒼太」
そう呼びかけるガルルモンの声は、優しい。
「空を見て。……光が、薄くなってるのがわかる?」
「あれはもうすぐ消える。だからもう、大丈夫だ」
「おいおいおいおいマジかよおい……やめろよ……! 俺が帰れねぇじゃねえか……!」
「それは、嘘だ」
しかしブギーモンに対しての声は、氷のように冷たかった。
「お前たちが何なのかは……お喋りだった方のブギーモンが、聞きもしないのに教えてくれた」
「……っあのクズ野郎……」
「蒼太。花那」
コロナモンは、じっと氷の壁を見つめた。
「もっと早くに来られなくてごめん。怖かったよね」
氷の壁が、ゆっくりと崩れていく。
氷越しで見ていた時より、デジモン達の傷は痛々しかった。
それ以上に。二人を見つめるコロナモンとガルルモンの目が、悲しそうだった。
「ガルルモンはコイツを連れて、あの場所に戻るよ。俺は君たちを家に送る。……それでいいね?」
蒼太は俯く。だが、花那は泣きながら「いやだ」と声を震わせた。
「だって……あのね、私たち、ずっと怖くて、昨日から」
「……うん。そうだよね。……そうだったよね」
「だから、だからごめんね。二人とも、そんなにケガしてるのに。でも私……まだ、二人と一緒にいたい」
家に帰るのが怖かった。二人がいない場所で過ごすのが怖かった。怖くて、怖くて、たまらなかった。
「……死にたくないよ……。だからお願い、……私たち、守ってて……」
◆ ◆ ◆
→ Next Story